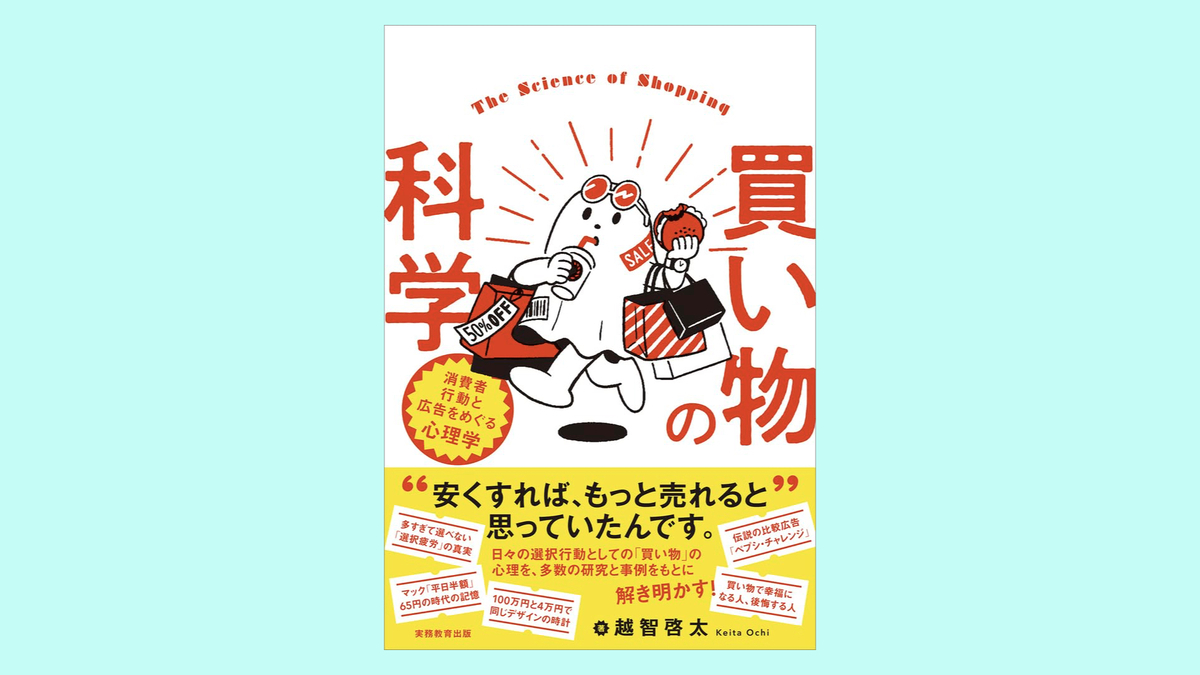お客様が、これ買いたいと思ってくれるようなそんな方法・技術について書かれています。
20全部をやる必要はないかと思いますが、こういうことを行なっていると変わっていくだろうと感じます。
ということで、20のうちのいくつかを簡単に紹介します。

- 『売れている会社に共通するこれ買いたい!をつくる20の技術』
- 『これ買いたい!をつくる20の技術』のここに注目・言葉・名言
- 信頼には理由がある
- 誰がどのように売っているか
- あわせて読みたい
- 『売れている会社に共通するこれ買いたい!をつくる20の技術』
- 今日の読書「ビジネス書をチカラに!」
『売れている会社に共通するこれ買いたい!をつくる20の技術』
博報堂買物研究所
目次
第1章 “買いたい”を“盛り上げる”7つのツボ『LOVE&BOOST』(偏愛性 自分の“好き”を表現できると買いたくなる;ストーリー性 そんな秘話を聞いたら誰だって好きになっちゃう ほか)
第2章 “買ってもいい”を“盛り上げる”7つのツボ『REASON&BOOST』(限定感 限りあるチャンスはものにしたい;フィット感 自分にぴったり!が欲しいの鍵 ほか)
第3章 “買いたい”を“維持”する3つのツボ『LOVE&KEEP』(マイペース 気軽に無理なく買えるのがありがたい;フリクションレス イライラがないだけで買物が楽しくなる ほか)
第4章 “買ってもいい”を“維持”する3つのツボ『REASON&KEEP』(信頼感 安心の実績 これを買っておけば間違いなし;根拠・理由 根拠で確信 納得して買物したい ほか)
第5章 ふたつのツボを掛け合わせ新たな相乗効果を生む6つの上級テクニック(ツボの掛け合わせで「強い購買行動」をつくる;ナナメの関係1 ラブ・クロスでつくる「最適解」 ほか)
『これ買いたい!をつくる20の技術』のここに注目・言葉・名言
「背景にあるストーリーに共感すると買いたくなる
「ストーリー性」を感じて買いたくなる瞬間は、以下ふたつが挙げられます。
1 こだわりや、開発背景に驚く
2 パーパスや想いに共感する
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
まずは、1こだわりや、開発背景に驚く、についてです。
商品が市場に登場するまでには様々な物語が生まれます。
誰がどんな想いでどんな過程を経て作られた商品なのか、背景にあるストーリーを知ることで共感が生まれて、生活者の買いたい気持ちが高まります。
ピックアップされるストーリーとしてよく見られるのは、企業の歴史、商品開発過程、販売してからの物語です。」(p.38)
「ストーリー性」を感じて買いたくなる
ストーリーから買いたくなるというのはあると思います。
開発ストーリーなどを見ると、気になる、欲しくなるというのはありますよね。
背景を知ったことで、買う。
さらに、満足感も高まるというのはありますね。
信頼には理由がある
「商品、売場、店員、売り方・・・
信頼には理由がある
「信頼感」を感じて買いたくなる瞬間には次のふたつがあります。
1 売り方から品質の確からしさを感じる
2 第三者評価や売り手の本音がわかる
それぞれ解説します。
まずは、1 売り方から品質の確からしさを感じる、についてです。
生活者は、買物をする際に「この商品はいい商品に違いない」という確信が持てるようになる情報を探しています。
例えば、含まれる成分や産地、製造過程などが公開されていると、商品を購入する際の不安を軽減できます。
近年ではECの普及により、選べる商品の幅が急数に広がりました。
ECが普及する以前は、リアル店舗で陳列された商品を購入していました。
店舗に陳列できる商品数には物理的な制約から限界があるため、商品を仕入れるバイヤーが、生活者のニーズを見極めて売れる
商品だけを選定します。その結果、選択肢は限られるものの、バイヤーがセレクトした生活者のニーズに合う商品群から商品を
選ぶため、失敗する確率はそれほど高くなかったと言えます。
しかし、ECでは陳列する際の物理的な制約がありません。
バイヤーのセレクトではなく、出品者が売りたいものを直接買えるようになったため、商品の多様性が広がり、生活者はこれまでリアル店舗では買えなかったメーカーの商品も買うことができるようになりました。」
(p.225-226)
誰がどのように売っているか
ECでも、大手であれば、なんとなく安心感というか信頼感がありますよね。
誰が売っているのか、どのように売っているかで、買うか買わないかは変わってくるところがあります。
いずれにしても、信頼してもらえるかどうかは、買うか買わないかで大きいでしょう。
信頼を得られるような工夫があると、違ってきますよね。
取り入れたいと思ったこと
このほかにも、あと18ほどあります。
偏愛性や自己投資、フィット感などです。
こういったところを意識して、伝えていくことで、買ってもらいやすくなると思いました。
取り入れたいですね。
あわせて読みたい
こちらは、エモ消費について書かれています。
ここから、エモマーケティングの考え方や手法を説明されています。
エモ消費などに興味がある方が読まれると、参考になることが見つかると思います。
『売れている会社に共通するこれ買いたい!をつくる20の技術』
おすすめ度
★★★★☆
これ買いたいとお客様に思ってもらう20の技術について書かれています。
これらを組み合わせて行うと、買ってもらいやすくなると思います。
参考にしたいですね。
おすすめしたい方
マーケティング担当者。
経営者。
今日の読書「ビジネス書をチカラに!」
「ストーリー性」を感じて買いたくなる
ストーリーがありますか?
 メルマガで読みたい方は、ぜひご登録を!
メルマガで読みたい方は、ぜひご登録を!

![売れている会社に共通する これ買いたい! をつくる20の技術 [ 博報堂買物研究所 ] 売れている会社に共通する これ買いたい! をつくる20の技術 [ 博報堂買物研究所 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5223/9784847075223_1_4.jpg?_ex=128x128)


![顧客を見れば、戦略はいらない 解像度を上げるボトムアップマーケティング [ 川端 康介 ] 顧客を見れば、戦略はいらない 解像度を上げるボトムアップマーケティング [ 川端 康介 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6445/9784296206445_1_28.jpg?_ex=128x128)
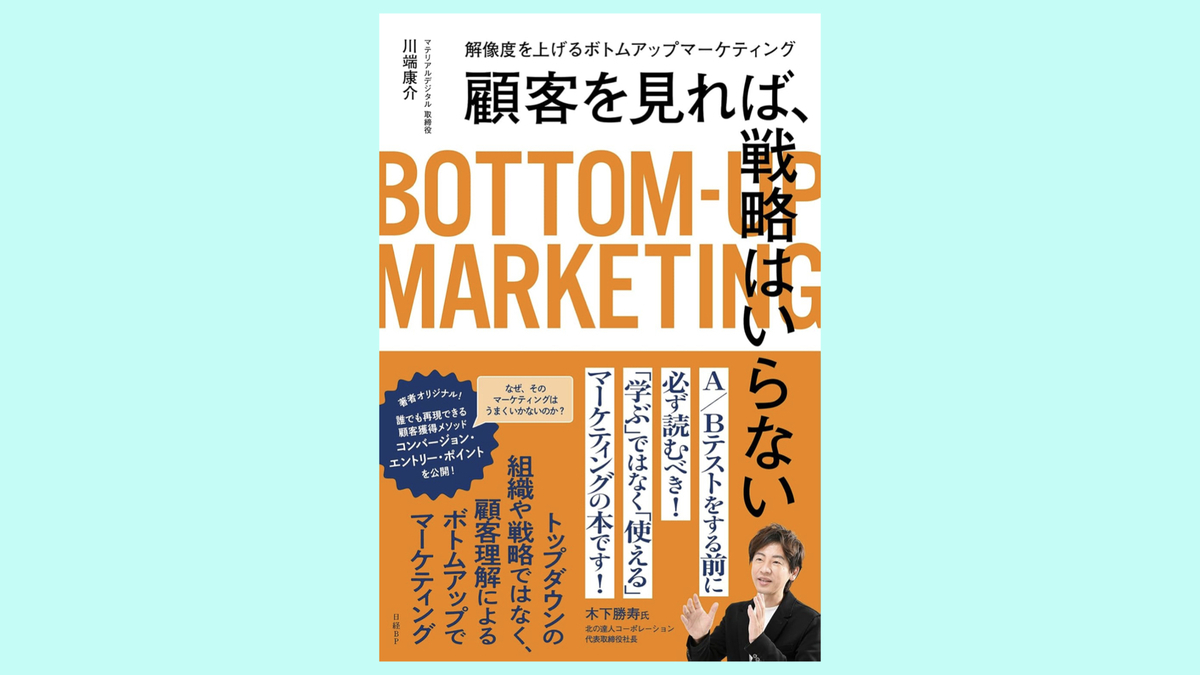


![確率思考の戦略論 どうすれば売上は増えるのか [ 森岡 毅 ] 確率思考の戦略論 どうすれば売上は増えるのか [ 森岡 毅 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5282/9784478115282_1_4.jpg?_ex=128x128)
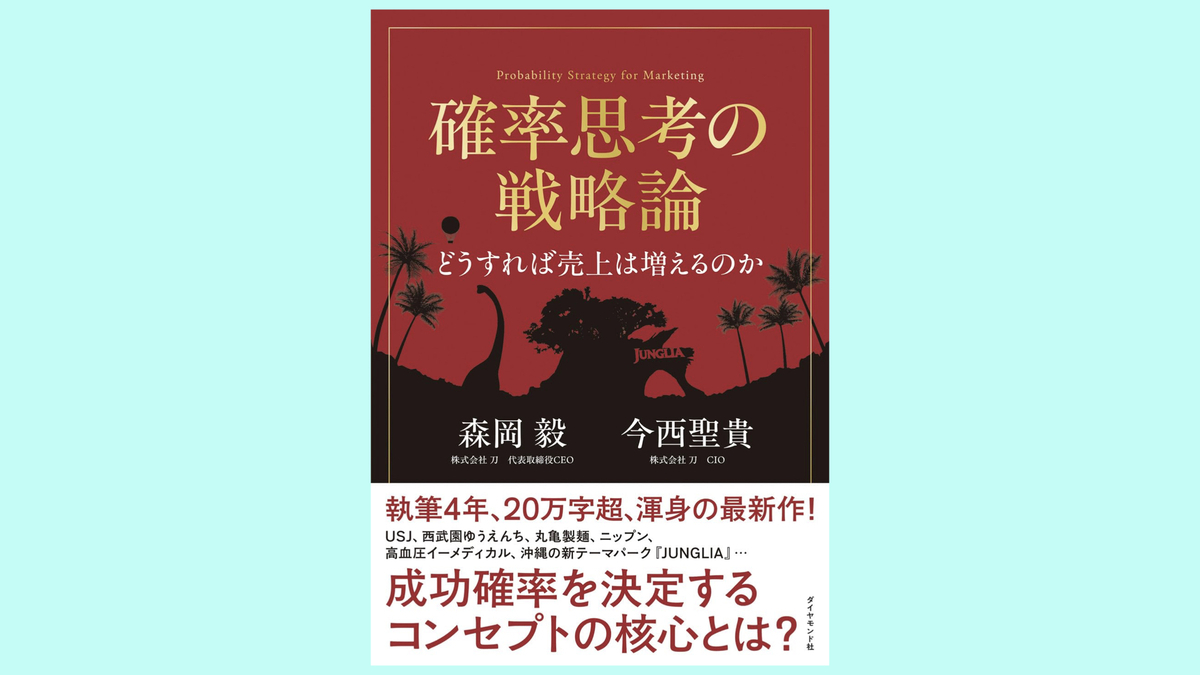


![このオムライスに、付加価値をつけてください (一般書 488) [ 柿内 尚文 ] このオムライスに、付加価値をつけてください (一般書 488) [ 柿内 尚文 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5162/9784591185162_1_69.jpg?_ex=128x128)
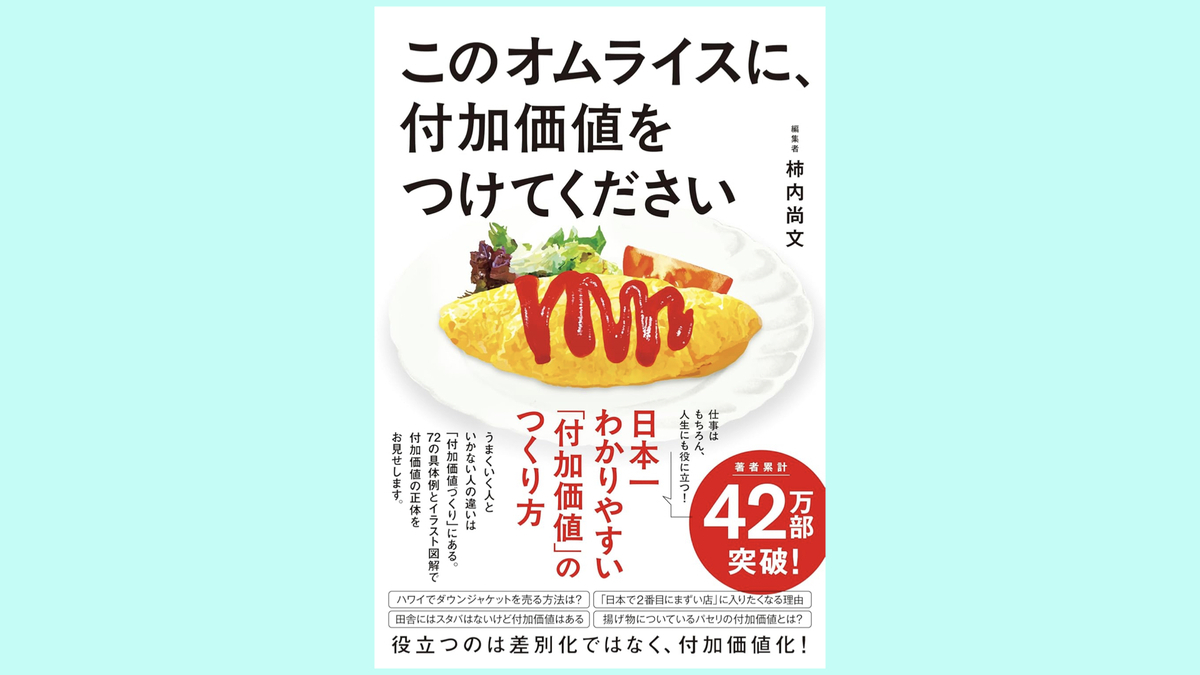


![「あたりまえ」のつくり方 ビジネスパーソンのための新しいPRの教科書 [ 嶋浩一郎 ] 「あたりまえ」のつくり方 ビジネスパーソンのための新しいPRの教科書 [ 嶋浩一郎 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3324/9784910063324_1_2.jpg?_ex=128x128)
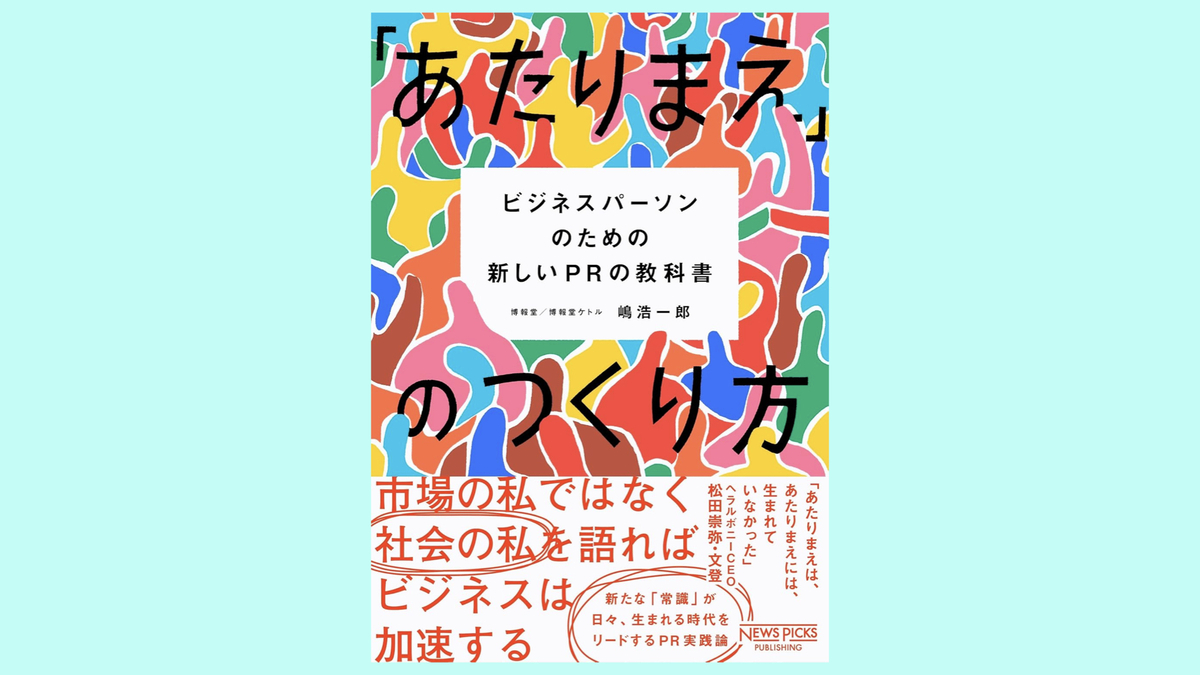


![SNSはキーワードが9割 [ 三浦孝偉 ] SNSはキーワードが9割 [ 三浦孝偉 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3262/9784798073262_1_3.jpg?_ex=128x128)


![売れる「値上げ」 [ 深井賢一 ] 売れる「値上げ」 [ 深井賢一 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3774/9784413233774_1_3.jpg?_ex=128x128)


![幸せな仕事はどこにある 本当の「やりたいこと」が見つかるハカセのマーケティング講義 [ 井上 大輔 ] 幸せな仕事はどこにある 本当の「やりたいこと」が見つかるハカセのマーケティング講義 [ 井上 大輔 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7583/9784492047583_1_2.jpg?_ex=128x128)


![小さな会社の売れる仕組み [ 久野 高司 ] 小さな会社の売れる仕組み [ 久野 高司 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2893/9784866802893_1_2.jpg?_ex=128x128)
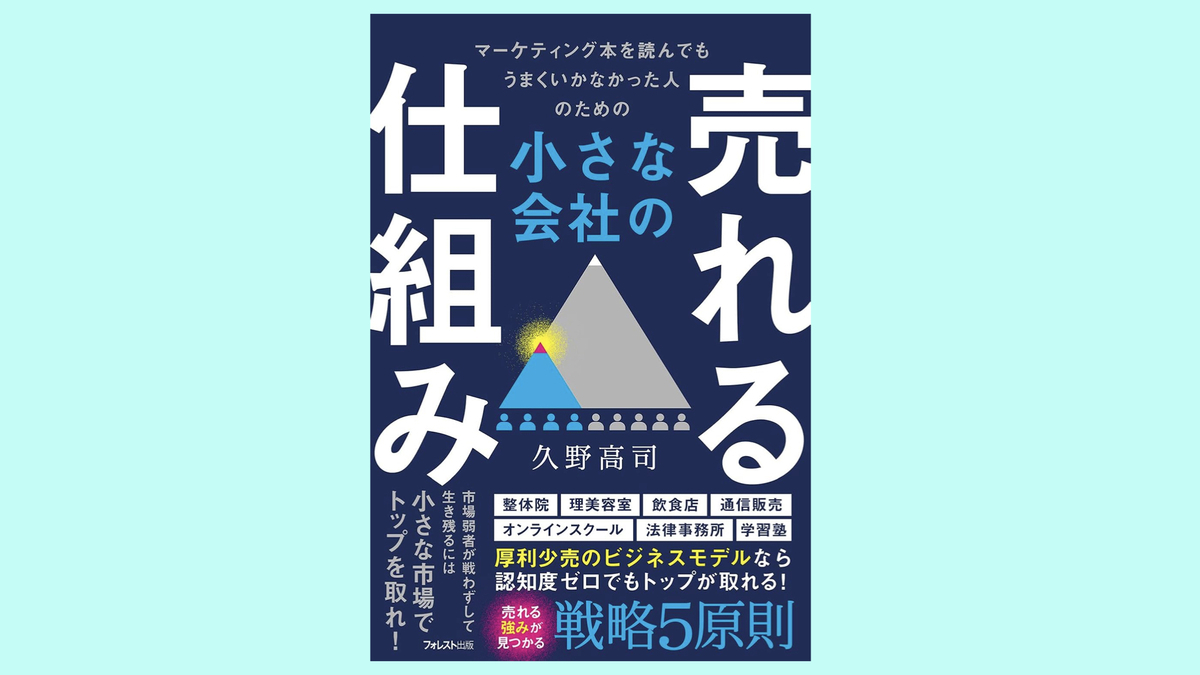


![買い物の科学 消費者行動と広告をめぐる心理学 [ 越智 啓太 ] 買い物の科学 消費者行動と広告をめぐる心理学 [ 越智 啓太 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4933/9784788914933_1_3.jpg?_ex=128x128)