経済学者のすごい思考法ということで、考え方などが書かれています。
貧困や気候変動、幸せなどを経済的な視点などから考えると、どうなるかといったことが説明されています。
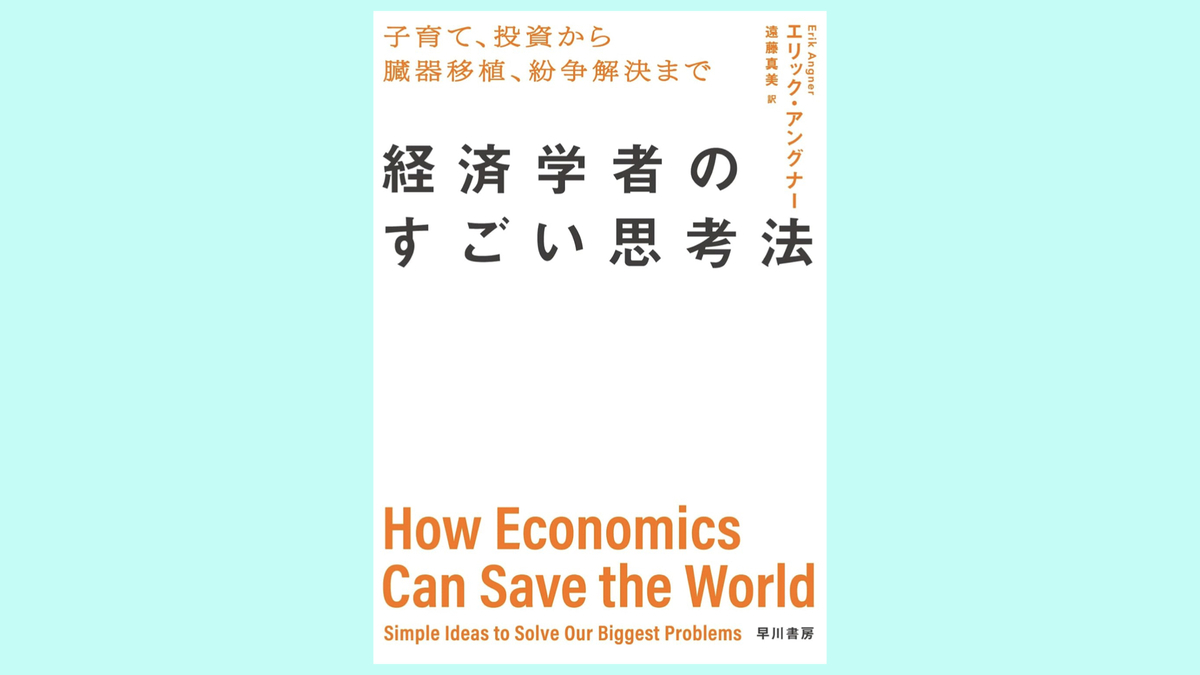
- 『経済学者のすごい思考法: 子育て、投資から臓器移植、紛争解決まで』エリック・アングナー
- 『経済学者のすごい思考法』のここに注目・言葉・名言
- 炭素税
- 取り入れたいと思ったこと
- あわせて読みたい
- 『経済学者のすごい思考法: 子育て、投資から臓器移植、紛争解決まで』
- 今日の読書「ビジネス書をチカラに!」
『経済学者のすごい思考法: 子育て、投資から臓器移植、紛争解決まで』エリック・アングナー
目次
序章 世界を救うには
第1章 貧困をなくすには
第2章 心を整えながらしあわせな子どもを育てるには
第3章 気候変動を食い止めるには
第4章 悪い行動を変えるには
第5章 必要なものを必要な人に届けるには
第6章 しあわせになるには
第7章 謙虚になるには
第8章 お金持ちになるには
第9章 コミュニティをつくるには
第10章 終章
『経済学者のすごい思考法』のここに注目・言葉・名言
「世界中の人たちの生活や選択を調べて二人が驚くのは、最貧困層の人でさえ、ほかのすべての人となにも変わらないことである。貧しい人はお金が足りない、場合によってはひどく足りないが、それ以外の点では、ほかの人たちよりも合理性が劣っているわけではない。バナジーとデュフロに言わせれば、まったく逆である。「貧しい人は、持っているものがあまりにも少ないからこそ、選択をするときにはとても慎重に考えることが多い。生きていくだけでも、高度な経済学者にならなければいけないのだ」。貧しい人に欠けているのは、知性でも、好奇心でも、人柄でも、生きる意欲でもない。
足りないのはお金であり、資源であり、機会である。賢明な政策が実行されて、必要なものが与えられるようになれば、貧しい人びとがよりよい暮らしを送れるようになる。そして、貧しい人びとの暮らしがよくなれば、わたしたち全員が「人間らしく生きることのできるよりよい世界」で暮らせるようになる。」
(p.35)
貧困層でも、合理性は変わらない
貧困層が、合理性がなくて、貧しいわけではないということです。
むしろ、選択をする時には、慎重になるとのこと。
お金や機会があれば、より良い世界になるということですね。
経済学で、そのような機会が増えるような政策ができると良いなと思います。
炭素税
「輸送用燃料の増税はどのような影響をもたらしたのか。アンデションは現実のスウェーデンと“仮想”スウェーデン(調査期間中に輸送用燃料に炭素税とVATがかからなかった点を除けば、スウェーデンとよく似ている架空の国)を比較している。
調査の結果は、炭素税が二酸化炭素の排出を抑えることを示すものとなった。
炭素税が導入され、VATが課されるようになった後、スウェーデンの輸送セクターが排出する二酸化炭素は11パーセント近く減った。それに最も寄与したのが炭素税だったのだ。
その一方で、炭素税が国内総生産(GDP)の足かせになったことを示すエビデンスは見つからなかった。炭素税はGDPにマイナスに作用する、炭素排出量が減るのは経済全体が減速するからだという説がある。しかし、スウェーデンのデータはそのようなことを示していない。マイナスに作用するどころか、現実のスウェーデンのGDPは仮想スウェーデンのGDPをわずかに上回った。
理論上でうまくいくものは実践でもうまくいくように見える。炭素税の効果は十分に大きくはなかったかもしれないし、排出基準を設けるなど、ほかの介入で補完する必要はあるだろう。だが限界においては、炭素税の導入は想定どおりの効果を生んだ。温室効果ガスの排出は大きく減った。」
(p.90)
炭素税は、経済成長の足かせになっていない
炭素税が二酸化炭素の排出を抑えることになるということです。
また、経済成長の足かせにもなっていないようです。
だとしたら、炭素税を導入するのは良さそうです。
このようなエビデンスや調査から、経済や環境の両立を考えられるというのが経済学の1つの考え方なのだと思います。
取り入れたいと思ったこと
「そうしたシナリオで個人の行動を変えるには、ほかの人の行動と期待を変えることだ。ほかの人の行動に関する誤解を正すだけでは足りないだろう。
逆説めいてはいるが、それほど矛盾してはいない。
ここでは、全員の行動をほぼ同時に変えることがカギになる。悪い行動を変えるのがむずかしい最大の理由は、その集団がすでに安定均衡にあると思われることだ。一人ずつ行動を変えることはできない。だれか一人を説得できても、すぐに考え直してやめてしまう。だが、十分に大きな集団を説得できれば、ふと気づくと別の安定均衡にいる、ということになるかもしれない。運がよければ、新しい均衡は古い均衡よりよくなる。」(p.110)
行動を変えるには、集団の行動を変える、期待を変えることということです。
簡単ではないかもしれませんが、いずれにしても、期待を変えて、行動を変えることで、変わる可能性があるということです。
今どんな期待を持っていて、どんな期待に変わったら、望ましい行動に変わるのか。
そんなことを考えて、できることは何かを考えると、集団や個人の行動を変えられるのかもしれません。
あわせて読みたい
『絶望を希望に変える経済学 社会の重大問題をどう解決するか』
アビジット・V・バナジー,エステル・デュフロ
こちらは、ノーベル経済学賞を受賞したアビジット・V・バナジー氏とエステル・デュフロ氏が、社会的な問題に関連する経済学などについて書かれています。
経済や経済学に興味がある方は読んでみてください。
『経済学者のすごい思考法: 子育て、投資から臓器移植、紛争解決まで』
おすすめ度
★★★★☆
経済学者の思考法ということで、考え方などが書かれています。
経済学的視点で、考えたい方が読まれると、参考になることが見つかると思います。
おすすめしたい方
ビジネスパーソン。
経済学的視点で考えたい方。
今日の読書「ビジネス書をチカラに!」
貧困層でも、合理性は変わらない
経済学的視点で見てみる
 メルマガで読みたい方は、ぜひご登録を!
メルマガで読みたい方は、ぜひご登録を!

![経済学者のすごい思考法 子育て、投資から臓器移植、紛争解決まで [ エリック・アングナー ] 経済学者のすごい思考法 子育て、投資から臓器移植、紛争解決まで [ エリック・アングナー ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3802/9784152103802_1_4.jpg?_ex=128x128)
